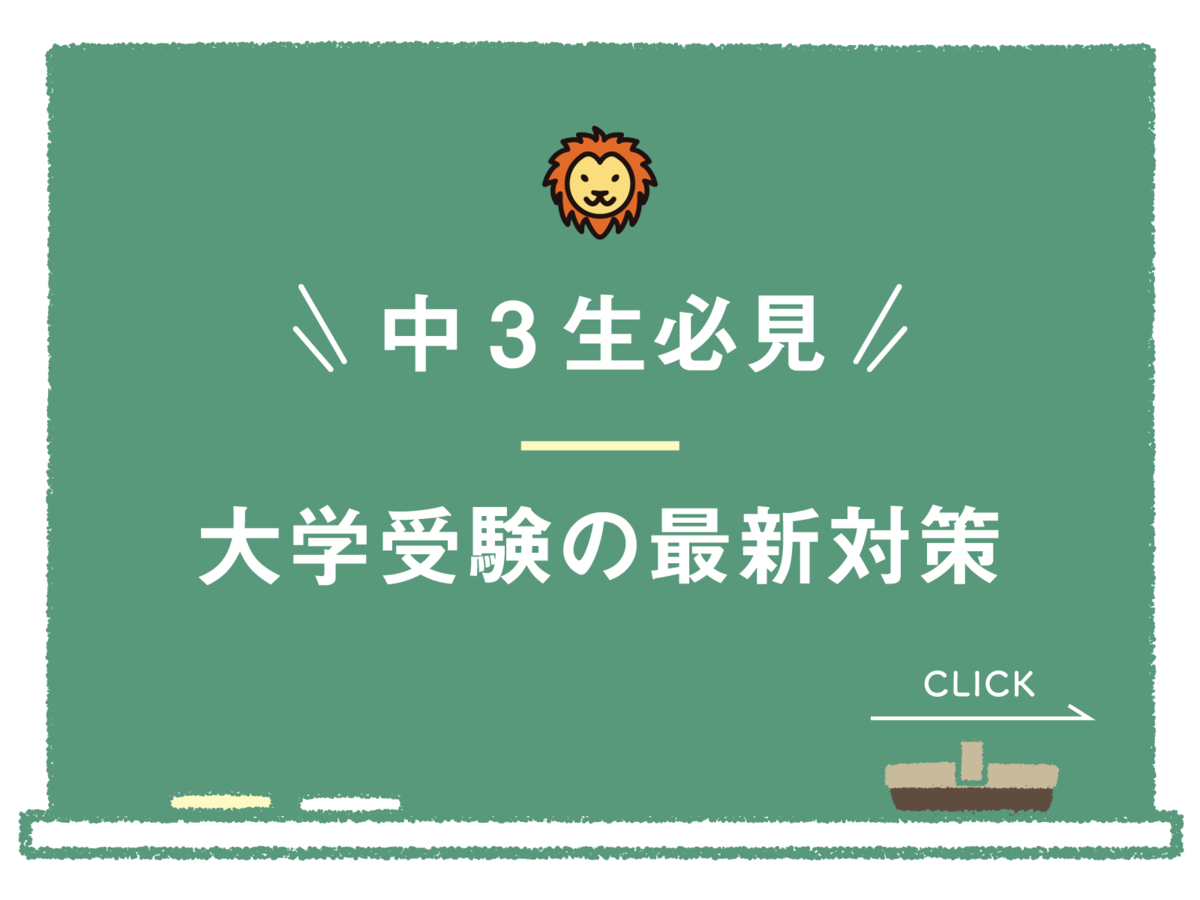
2025年に待っている大学入試の大きな改革、現在の中学3年生が最初の世代に
昨冬の大学入学共通テストでは、記述問題の導入や英語において4技能を評価するための民間の外部試験の導入が検討されるも撤回され、大きな話題になりました。
今回の変更も従来のセンター試験から新しい大学入学共通テストと呼び方が変わり、変更の印象が強く持たれました。
しかし、大学入試の改革はこれに留まりません。これまでの流れは2025年に予定されている最終的な変更への階段なのです。
およそ10年に一度改定される指導要領は小学生から徐々に導入されていきます。
そして今回の改定は現在の中学3年生が大学受験を迎えるときに全面的に反映されます。
ここでは大きく変わる2025年の大学受験をどう迎えればよいか、少し先の話にはなりますが、予行演習をしたいと思っています。
入試の教科や科目の変更。プログラミング必修科に伴い「情報I」が教科に
新学習指導要領に沿って大学入学共通テストに出題される教科・科目は現在の6教科30科目から7教科21科目に再編されると報道されています。
具体的な変更としては次のとおりです。
<英語>
一旦見送りとなったものの、スケジュール上では2025年の試験から民間の外部試験となります。
<数学>
数学Ⅱ・Bに数学Cが追加され数学Ⅱ・B・Cとなります。
<地理歴史>
日本史と世界史を両方必要とする歴史総合が追加されます。
日本史を選択した場合でも世界史を選択した場合でも、それぞれ両方の学習をする必要があります。
<理科>
物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎の4つをまとめた科目が新設されます。
※ただし、高校卒業に当たっては上記のうち3つを履修すれば可となっています。
<公共>
新しい必修科目。現代社会が廃止されます。
知識習得ベースではなく課題解決を重視する科目のため、試験方法も工夫されるのではと考えられています。
<情報I>
いわゆるプログラミング必修化といわれているものです。
試験問題の案が示されていて、架空の言語を用いたプログラミングの問題や、情報リテラシーについて出題される見込みです。
上記のほか、国語・数学に加えて、地理歴史・公民・理科においても記述式問題の導入が検討されています。
2025年に向けた入試対策の変化と最新対策
今後の議論もあると思いますので、定かなものではありませんが、現時点で考えられる対策は次のとおりです。
・論理立てて考える力、説明する力をつける
記述式問題の導入など、従来の選択式から出題形式が大きく変わる可能性があります。答えに辿り着く過程を順を追って相手に説明できる力をつける必要があるでしょう。答えがあっていたかどうかに一喜一憂せず、考えの過程を再確認するような勉強が大切です。
・英語と数学へのアレルギーをなくして情報Iに備える
情報Iは教科として扱われ、国として大きくプログラミング教育へ舵を切った形となっています。
プログラミングには英語や数学の要素が出てきます。そこにアレルギーがあるとどうしても頭の中に入っていきません。今のうちから英語・数学アレルギーを無くしておきましょう。
・受験対策だけでなく、幅広く関心を持つ
各教科や科目の出題範囲が拡大傾向にあり、従来のように必要科目だけに的を絞った勉強がしにくくなる可能性があります。
幅広く興味関心を持ち、「捨てる」科目をなるべく作らないようにしましょう。



